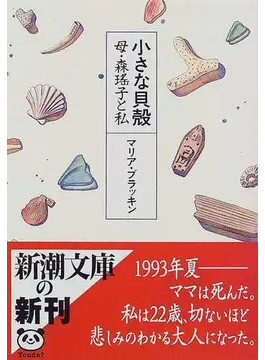
森瑤子の次女であるマリア・ブラッキンが、母との思い出を綴ったこのエッセイを出版したのは、作家の死からわずか2年後のことである。森瑤子の名前すら書店では余り見かけなくなった今、こんな、便乗商法のように出版された、彼女の娘がたった一回上梓した本を読む人なんて、ほとんどいないだろう。
この忘れ去られた本に興味が湧いたのは、森瑤子をモデルとした篠田節子の『第4の神話』で、かなりこきおろされていたからだ。小説では、死後まもなく世間から忘れかけられている作家を何とか盛り上げて一花咲かせる為に、彼女の娘が書いたという建前で、主人公がゴーストライターとなってエッセイを書き上げるのである。
篠田節子は、全体的にこの小説では、モデルの森瑤子に辛口だが、娘の扱いはある意味もっとひどい(笑)それで、返って、捻くれ者の私は、実際に彼女の娘が勢いで出したとおぼしきこの本を、読んでみたくなってしまった。
たしかに、全体としては、少々甘ったるいエッセイではある。しかしまあ、実の母の死の直後に書かれたことを思えば、多少美化し過ぎる傾向があるのは致し方ないのではないか。母への感情移入が強過ぎると言うか、母の人生を客観的に捉えるよりは、必要以上に自己犠牲的に捉えてしまうのは、当たり前だと思う。
そのあたりを割り引いて読めば、作家・森瑤子の一つの姿を知るには中々に面白い本である。結婚相手であるアイヴァン・ブラッキンとは仮面夫婦だった、とか、過度の借金と仕事で家庭は崩壊寸前だった、とか、世間では色々取り沙汰されたようだが、そんなことは、夫婦や家族以外の者がいちがいに判断できるようなものでもない。娘のマリアが見る母・森瑤子の姿は、死の直後で多少美化されているとしても、読む者の心を十分に温めてくれる。
例えば、三崎の海辺の別荘で過ごす週末、まず部屋に入るとゲジゲジがいないかチェックし、ゲジゲジを見るたびに「アイヴァーン、へールプ!」と碑銘をあげていたとか、母が仕事の息抜きに本を読んでいる岩場は「マミーズアイランド」と呼ばれていてた、とかいうエピソード。
様々な夢の島に囲まれた三浦の海は私のお庭だった。子供の心にしか理解できない秘密のお庭だ。そこにはあらゆる友達がいて、あらゆる生命、感覚、様々な風、光、熱、海があった。その自然の美をおもちゃの代わりに与えてもらった私たちはどんなお金持ちの都会の子供より幸せで、恵まれていたと思う。
例えば、寝るまえにサンタのためのブランディーと、母のてづくりのミンスパイを暖炉の横に置いておくクリスマスイブ。「自分たちが入れるくらい大きなお人形さんのお家がほしい」という手紙通り、パティオに車一台くらいの大きな木製の家が置いてあったのを発見したクリスマスの朝。
父とははが子供のためにあれだけのことをやり通したという気合と優しさに、私は父と母の愛をつくづくと感じる。サンタは結局存在しなかったが、そこにはサンタの心が存在した。父の心にも、母の心にも。今になって私は、サンタは人間という形をもった存在ではなく、子供に夢を信じることの暖かさ、気持ち良さを初めてかんじさせる、かたちを変えた親の愛だと思う。
それから、私が個人的に好きだったのは、なんと言っても彼女の美食エピソードである。「夢の食卓」は、森瑤子の美食っぷりを存分に語ってくれる、食いしん坊にはたまらない章だ。グレイビーとミントソースを添えたラムレッグ、絶品のパイやマッシュドポテトなど、一から勉強して上達したイギリス料理も素敵だが、イワシの缶詰を醤油と唐辛子で炒めて七味を少々降りたし、細かく切った万能ねぎと千切った海苔をたっぴりとのせて熱々のご飯にかけた特製の「与論どんぶり」は、一口でいいから食べてみたくなる。
母に教わったことは計りしれないほど沢山あるが、その一つはもちろんん、家族に作る食事の気合いと愛情がどれほど大切なことかだ。
彼女は食べることの喜びはもちろん、食べることについての美学も持っていた。そして食べる時のその雰囲気と設定にもこだわりを持った。
森瑤子になる前の食卓や食事はとても素朴だった。汚れたテーブルクロスの真ん中にはバラが一本ガラスのコップにさしこまれていて、その赤いバラはかさかさに枯れてしまうまでそこに置いてあった。バラの美しさの限界に気が付くと、母は今度は花びらをちぎり、それを水の入ったスープ皿のような器に浮かべる。その一本のバラは二週間ほど、食卓を一生懸命に飾ろうとしていた。
このバラのエピソードがあってこそ、森瑤子になってからの彼女の美食へのこだわりっぷり《場所によって、食卓も変わった。東京では都会を忘れさせる田舎風の器を使ったり、地中海の海を思い出させるほどのあざやかなブルーの食器を使ったり、イギリス料理の時はイギリスの田舎風のお洒落でかわいらしい食卓を作った。与論島の別荘では、島に合った与論焼や古い陶器を揃えて食卓を楽しんだ。ワイングラスやグラスはすべて透き通った与論の海と同じ色のブルーの物、湯呑みもわざわざ京都で買ったシンプルな物を集めた。箸置きはビーチで拾った白いサンゴのかけらを使ったり、灰皿もビーチで見つけた大きめの貝殻を使っていた。》が、燦然と輝いて読者の目に映ってくる。やっぱり、森瑤子はただバブルに踊らされたスノッブな作家だったわけじゃないのよ、と、誰に対してだか分からない反論をしたくなる。
その他にも、娘と2人のバリ島旅行で怪しげなキノコを食べてハイになってしまった、とか、与論島の別荘で娘と泥酔して「これがママの夢なのよ!これが森瑤子が叶えた夢なのよ!」と叫びまくった後、トイレでゲロゲロになっていた、とか、微笑ましいエピソードがあって面白い。これだけのことをやって、これだけの愛を貫いて、例え痛みに引き裂かれて若くして命を散らしたとしても、それは彼女の本望だったんだろう、と思えてくる。森瑤子ファンなら、一度読んでみてもいいと思う本だ。








コメント