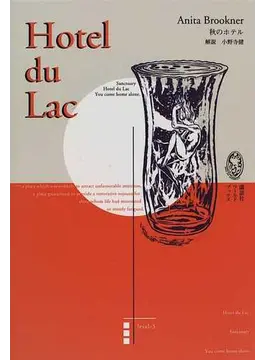
この小説を読んでみようと思ったきっかけは、世界的権威ある文学賞ブッカー賞を受賞している作品ということもあるが、著者の経歴に興味を惹かれたからである。アニータ・ブルックナーは、ロンドン生まれのイギリス人女性作家だが、ロンドン大学の附属コートルード美術研究所で美術史の博士号を取得し、同研究所やケンブリッジ大学で教授を務めたという、れっきとした美術史家なのだ。
ストーリー。主人公は、ロンドン在住で、ロマンチックな恋愛小説を書いているアラフォー女性作家である。彼女は、ジュネーブ湖畔の知る人ぞ知る由緒正しいこじんまりとしたホテルに、あるスキャンダルから身を隠すため逃れてくる。同じホテルに逗留している、裕福だが何か欠落したような謎めいた客たち。彼らとの交流を通じて、既婚男性との不倫関係、堅実で裕福な中年男性との婚約、そして結婚式当日に突然心変わりして婚約破棄となったスキャンダル、など、彼女の過去を振り返る数日間を描いている。
読み終えての第一の感想は、「これがブッカー賞か・・・」というものだった。貶しているのではない。言い方が難しいのだが、深遠なテーマとか壮大なストーリーとかからはかけ離れた、どちらかと言うと、そういうものとの対極にあるような、ミクロで繊細な世界を描いた作品なのである。これにベストオブザイヤーを与えるブッカー賞が面白いと言うべきか、とにかく、ノーベル賞候補には絶対ならないだろうな、と思う。(ブッカー賞とノーベル賞の違いについては、『世界の8大文学賞』の記事を参照)
主人公の感情表現が抑制されていて、ストーリーはすごく静かに淡々と進行していくのだが、読み終えた後には、なんだかじわりと胸に迫るものがある。まず、硬質で静謐な文章がすごく美しい。抑制されている中に、緊張感と繊細さが漲っている心理描写。そして、動きがあまり感じられないストーリーが進行するにつれ、主人公の過去やトラウマが、まるで、濃霧の中からジュネーブ湖が見え隠れするかのように、徐々に明らかになっていく、という、構成的な面白さもある。文学的に完成度がすごく高いし、エンディングは結構悲壮なものなのだが、読後の印象はすごく軽くてちょっと掴みどころがないような、不思議な感覚。
思えば、イアン・マキューアンの『初夜』とか、パオロ・ジョルダーノの『素数たちの孤独』とか、現代の、国際的な評価の高い作家の作品には、同じような特徴があるのかもしれない。文章の端麗さや構成的な巧みさ、非常に繊細でミニマルな世界観、不安定さと虚無感と、そして、それさえ突き抜けてしまったような妙な爽やかさ、軽やかさ。
19世紀から、欧米の文学にとっての最大のテーマは「神なき世界をどう生きるか」だった。それがあまりに煮詰まって、ポストモダンと多様性の時代があって、そして今、文学には、感性とミニマリズムと軽やかさが求められているのかもしれない。と言っても、このテーマは、まだちょっと自分の中でまとめ切れていないので、今後検討することにしよう。
あと、個人的に印象に残ったのは、「母と娘の関係」というものが、サブテーマながら結構綿密に描かれているところである。これも、全世界を通じて、現代文学に扱われやすいテーマなのかなあ、と思ったりする。日本でも、このテーマの作品は実に多い。ものすごくめんどくさいテーマなので、これも、これ以上はここで掘り下げたくないが(笑)
彼女の小説は本作を含めて幾つか邦訳されているものの、美術批評関連の著作については邦訳がない。早稲田大学で英文学を研究されている北村有紀子さんという方がいて、アニータ・ブルックナーについての論文を幾つか発表されているのだが、それによると、《「美術史について書かれたものは、文学としても価値がなければならない」という信条を持っていたことがうかがえる》(論文『批評家としてのアニータ・ブルックナー』より)そうである。
美術史家としてスタートした彼女は、やがて小説を書くようになり、また、美術だけでなく文芸評論までその文筆活動を広げていく。そんな文章に並々ならぬこだわりを持つ彼女の美術評論。しかも、専攻は18、19世紀のフランスロマン主義絵画。うーん、読んでみたい。。。しかし、邦訳がないので原文に当たるしかない。。。って、こんなことなら、もっと大学時代にちゃんと勉強しておけば良かったじゃないか、、、(このブログでも何度か触れているが、私の大学時代の専攻は美術史学である)そんな、中年あるあるの一抹の後悔を覚えながら、今宵も無為に夜は更けていくのであった。






コメント