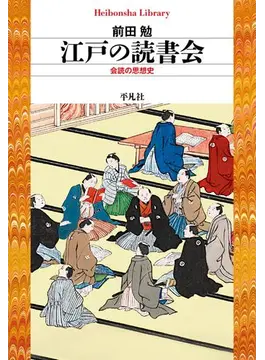
前回の記事で、本書の概要を簡単にまとめて見たが、読んでみて気になったことだけ以下に挙げておきたい。
一つは、会読文化における「遊び」の要素である。著者は、荻生徂徠が広めた会読には、元々「本読み会」的な遊びの要素があったのだとし、ホイジンガやロジェ・カイヨワの定義を引用してこう語っている。
遊びといえば、遊ぶことに人間の本質的機能があるとする『ホモ・ルーデンス』の著者、オランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガの次のような定義がある。
その外形から観察した時、われわれは遊びを総括して、それは「本気でそうしている」のではないもの、日常生活の外にあると感じられているものだが、それにもかかわらず遊んでいる人を心の底ですっかり捉えてしまうことも可能な一つの自由な活動である、と呼ぶことができる。この行為はどんな物質的利害関係とも結びつかず、それからは何の利得も齎されることはない。それは規定された時間と空間のなかで決められた規則に従い、秩序正しく進行する。またそれは秘密に取り囲まれていることを好み、ややもすると日常生活とは異なるものである点で、変装の手段でことさら強調したりする社会集団を生み出すのである。(『ホモ・ルーデンス』、高橋秀夫訳、中公文庫、1973年)
ホイジンガの遊び論を、遊びの多様性を強調することでさらに発展させたのが、ロジェ・カイヨワである。カイヨワによれば、遊びの主要項目は四つに区分できるという。サッカーやチェスやビー玉をして遊ぶアゴーン(競争)、ルーレットや宝くじで遊ぶアレア(偶然)、海賊遊びをしたり、ネロやハムレットを真似て遊ぶミミクリー(模擬)、回転や落下など急激な運動によって、自分の中に混乱狼狽の有機的状態を作る遊びをするイリンクス(眩暈)の四つである。会読はこのなかの競争という形をとるアゴーンに相当するだろう。(略)
カイヨワによれば、「競争とは、勝者の勝利が正確で文句のない価値を持ち得るような理想的な条件の下で競走者たちが争えるように、平等のチャンスが人為的に設定された闘争である」という。ここでは「その分野において自分が優れていることを認めさせようという願望」が原動力となる。
この本を手に取ったのは、日本における「サロン、クラブ、カフェなどの編集的文化が発生する場」に興味があったからだが、「遊び」の要素は、このサロン的文化に非常に重要な要素であると言える。ヨーロッパのサロンが、当初から、言葉遊びや文芸遊びの場として機能していたことは、『十七世紀フランスのサロン』などの著書を読んでも明らかだ。「サロン、クラブ、カフェなどの編集的文化が発生する場」では、ステイタスの匿名性が自由闊達な交流を生む原動力となっているが、「遊び」を通じて、ホイジンガのいう《日常生活の外》に出て、《どんな物質的利害とも結びつか》ないという関係を作りだす効果もあるだろう。
もう一点、興味を惹かれたのは、幕末から日本の近代に発展していく政治的思想の流れである。前回の記事で書いた通り、江戸時代を通じて儒学の学習方法として根付いてきた会読文化は、後期水戸学の活動などに結びついて、一気に政治勢力化した。後期水戸学は、水戸藩第九代藩主徳川斉昭を中心に、藤田幽谷・藤田東湖・会沢正志斎らによって、中国の兵書『孫子』を理論的枠組みとして打ち立てられた思想で、幕末の尊王攘夷思想の発信源となった。
すなわち、西洋を夷狄としてとらえ、これを打ち払えとする攘夷策は、文政八年(1825年)の外国船打払令を好機に、意図的に絶体絶命の「死地」(『孫子』)=戦争状態にひきずりこんで、国内の民心を統合するという戦術であり、また祭祀制度を通して、天皇を頂点とする階層秩序を再編する策もまた、民心統合を目的とする長期的な戦略であって、正志斎は、この兵学的な戦術・戦略論によって分散した「民心」を統合し、日本全体を「八州を以て城」とする国防国家建設を構想していた(拙著『近世日本の儒学と兵学』)。さらに「武威」の兵営国家を非常時戦時体制下のもとで立て直そうとする、軍事的な国家構想であったがゆえに、武士の支配層、とくに商品経済の進展によって困窮化した中下志層の武士たちに同調者を集めることができたのだ、と指摘した(拙著『江戸後期の思想空間』)
ところが、近世日本の国家意識のたかまりのなかで、日本を夷狄とみなすことにたいする反発が起こってくる。むしろ、日本が世界の中心に位置するのだというのである。いわゆるエスノセントリズム(自民族・自国家中心主義)である。ただ、その際、礼教文明を基準とすることはできないので、万世一系の皇統と武威がそれを代替する根拠となった。中国では、革命が頻発して、何度も王朝が交代してきたのに、わが日本では神代以来、皇統が変わらず安定しているうえに、古代以来、軍事力のすぐれた武威の国として世界に恐れられてきた、というのである。この二つの「歴史的事実」を根拠として、日本は世界に冠たる誇るべき国だという、いわゆる日本型華夷観念が、江戸後期には広く流通していた。後期水戸学の尊王攘夷思想は、この日本型華夷観念の典型だった。
幕末の尊王攘夷から、後期水戸学の相澤正志斎や吉田松陰らが提唱する「国体」論への展開、その背後には、他国との戦争状態をも恐れぬ日本型華夷観念を貫き通し、意図的に民意を鼓舞して統合しようという、戦略的な思想があった。
そして、本書によれば、明治維新後、会読は教育の場から姿を消すものの、その政治的運動は、自由民権運動に継承されていく。吉田松陰が、獄中の人間にまで「諸君」と呼びかけた会読の精神は、大衆に対する演説へ、三原理の一つである「結社性」は、民権結社へと、変化していくのである。
これまで見てきたように、こうした民権結社の「作為的に選択された組織」性(色川大吉『自由民権』)と会員間の平等性、そして内部での相互コミュニケーション性は、会読の原理そのものであった。とすれば、明治期の民権結社は江戸期の会読結社の発展形態として捉えることができるだろう。(略)自由民権運動の民主主義は、江戸時代の会読の内発的な発展の上に創り出されたものなのである。
『満洲国演義』シリーズの第3、4巻の記事でも書いたように、私の中で、戦前における「国体」思想の変遷と、明治「維新」と大正「デモクラシー」を経た後の自由民権運動のあっけないほどの衰退ぶり、は、大きな疑問として燻っている。言い換えれば、あれほどの軍国主義とファシズムを可能にした思想的バックグラウンドはどこにあるのか、そして、なぜ、これほどまでに「自由民権運動」は戦前の(いやあるいは戦後も)日本に根付かなかったのか、という大きな疑問。この問題はまだまだ勉強しなくてはいけないことが多くて私の中で整理できていないのだが、本書の「会読」を通じて、幕末から明治への思想の変遷を辿ることで、少し手掛かりが見えたように思う。






コメント