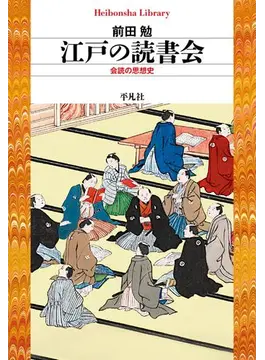
日本にあったサロンやクラブについて勉強していく中で、興味をもった本である。江戸時代の学習方法としてメジャーだった読書会という文化。元々は、儒学の学習方法から起こってきたものだと言う。
著者によると、儒学には元々「素読」「講釈」「会読」という3つの学習方法があった。漢文の意味内容を解釈せずに、文字のみを読み習い、暗誦することを目指した「素読」、先生が生徒隊の前で、経書の一章、或いは一説ずつを講解して聴かせる一斉授業形式の「講釈」、そして、同程度の学力をもつ上級者が、《一室に集って、所定の経典の、所定の章句を中心として、互いに問題を持ち出したり、意見を闘わせたりして、集団研究をする共同学習の方式(石川謙『学校の発達」、岩崎書店、1951年)》をもつ「会読」である。この学習方法は、幕末の藩校のみならず、蘭学や国学の私塾などでも採用されていた。本書は、この中の特に「会読」の歴史に着目する。
「会読」の学習方法には、3つの原理があり、これが「会読」という特殊な文化を読み解く一つの鍵となる。すなわち、「相互コミュニケーション性」「対等性」「結社性」の3つである。
参加者お互いの討論を積極的に奨励するという相互コミュニケーション性、参加者お貴賎尊卑の別なく平等な関係のもとで行うという対等性、読書を目的として、複数の人々が自発的に集会するという横の繋がりをもたらす結社性、いずれも、上意下達のタテの人間関係を基本にしていた江戸時代にあっては、その根幹を揺るがす力を内在する原理であったと言えるだろう。
(近世日本の国家で)上意下達のタテの人間関係が基本であった理由は、近世日本の国家が兵営国家であって、軍隊組織が秩序のモデルだったことに起因する。もともと、近世日本の国家は戦国時代の軍隊組織をそのまま凍結させた体制であった。そのため、命令–服従の軍隊組織の原理がそのまま天下国家を治める原理として通用したのである。そこでは、将軍を頂点とする統治者の命令な絶対であって、一切の批判は許されなかった。
科挙のない近世日本で、儒学が学ばれた一つの理由に、聖人になることへの強い希求があった。(略)この「人間本心」の平等の立場から(略))、人間的な成長の可能性を認め、どんな身分の低い者であっても、道徳的に完璧な人格者になれるのだと説いたのである。もちろん、そうした人格者は「忠義」「孝行」の人であって、身分秩序に反するものではなかった。しかし、そうだとしても、だれよりも立派な人間になろうとする点で、身分秩序のなかでの屈折した平等化への希求出会ったといえる。
こうした平等化への希求心を想起すれば、参加者が対等な立場で討論し合う会読の場は、もっとストレートに平等化が実現できる場だったといえるだろう。
よく知られているように、江戸時代、百姓一揆などの徒党を組むことは、厳しく禁じられていた。この大原則のなかで、俳諧の会や、狂歌の会などの「連」「社中」は禁じられていなかった。そのわけは、遊戯だからである。読書会、会読の会が徒党とみなされず、禁じられなかったのも、学問も漢詩、俳諧や狂歌と同一レベルのもの、一種の遊戯だと思われていたからであろう。たしかに、そうした遊芸の面を無視できないし、後にも述べるように、そこに積極的な意義があるのだが、儒学の経書を読むための明確な規則をもった会読結社の場合、そこから政治的な朋党を生み出していった点で、たんなる詩文結社とは異なる思想的な可能性をもっていた。
会読はまず儒学者の伊藤仁斎、そして荻生徂徠によって、儒学の能動的・主体的な学習方法として積極的に取り入れられた。
徂徠は、寛文六年(1666)江戸で、町医師荻生方庵の子として生まれた。十四歳の時、父が主君の館林侯徳川綱吉(後の五代将軍)から江戸払いに処せられ、二十五歳まで、一家は上総国を転々とし、苦しい生活を強いられた。江戸に戻ってから、芝の僧正寺前で塾を開き、三十一歳の時、将軍綱吉の寵臣柳沢吉保に仕え、綱吉の学問の相手を務めたこともあった。大石内蔵助ら赤穂藩の遺臣四十七人が吉良上野介義央の首級をあげた赤穂事件のさい、幕法に反した大石らに名誉ある死である切腹を命じた幕府の処置には、徂徠の考えが反映していたといわれる。宝永六年(1709)四十四歳、綱吉の死後、茅場町に私塾けん園を開き、多くの門人を育てた。主著は、古文辞学の方法によって朱子学を批判して、新たな儒学体系を展開した『弁道』『弁名』『論語微』、ほかに、八代将軍徳川吉宗の下問に答えて提出した幕政改革の書『政談』がある。
P89
徂徠は、弟子たちに会読の効用を説くだけでなく、自らも、儒学の学びという枠を超え、仏教僧までメンバーに取り入れて、中国語書物を翻訳する目的の「訳社」という文芸サークル的な結社を結成した。徂徠派によって広められた会読は次第にメジャーな学習方法となり、十八世紀中頃位は、江戸・上方で一つの流行となった。江戸の鬼才、大田南畝の『寝惚先生文集』には、徂徠派の会読を茶化すような文章も見受けられる。
会読は、亀井南冥の蜚英(ひえい)館、広瀬淡窓の咸宣園など、儒学者の私塾だけでなく、緒方洪庵の適塾など、蘭学の場でも積極的に用いられた。特に、緒方洪庵の適塾で、会読により《塾生たちが互いに切磋琢磨した様子は、『福翁自伝』に生き生きと描かれて》おり、本書でも、何度か引用されている。田辺聖子の『ほっこりぽくぽく上方さんぽ』では、この大阪の適塾跡を訪ねる章があり、まさに《生き生きと》適塾塾生達の猛勉強の様子が伝わってくるので、ここで紹介しておきたい。
やがて、会読は私塾だけでなく、熊本の時習館、佐賀の弘道館、金沢の明倫堂など、藩校にも取り入れられていく。背景には、時に他藩の人材も積極的に受け入れて、不足する人材育成を積極的に行おうとする、藩の意向があった。しかし、様々な問題が山積する幕末においては、会読は、自然と政治的議論の場になっていく。そして、尊王攘夷思想の礎となった水戸藩における後期水戸学の興隆、さらには吉田松陰が、獄中から一般民衆と会読を通じて行動を呼び掛けていくなどして、幕末の会読は、政治的影響力を増して、維新を準備していくことになる。
著者は、藤田省三の『維新の精神』を引用し、こう述べている。
藤田によれば、維新をもたらしたものは、佐幕か倒幕か、開国か攘夷か、といった路線問題にあるのではなく、一人一人が議論し、行動し、横に繋がった時に、維新が起こったのだという。藤田は、「横断的議論と横断的行動と現世的地位(ステイタス)によらずした「志」によって相集まる横断的連結とが出現した場合、その場合にのみ維新は維新となった」と説いて、「横議」「横行」「横結」によって、「幕藩体制の社会的脈絡(コミュニケーション形式)はくつがえされ、新たな社会的連結の構造が萌え出たのであった」と論じた。この藤田がいう横断的議論、横断的行動、横断的連結が生まれた場こそが、これまで見てきた会読の場だったのである。
このように、いわば明治維新の精神的母体でもあった会読文化だが、明治時代にうつり、学制と共に欧米の教授方式が導入されると、学びの方法、学びの場としての文化は次第に失われていく。身分制が廃止され、誰もが平等の機会を得る建前ができると、学問は立身出世の道具となり、純粋な学びの喜びを追求する自学学習ではなく、評価のしやすい知識・情報偏重の教育、現代にまで続く教育に変わっていくのであった。






コメント