ヴェネツィアを深く知るために必読な古典・名作の本8冊を紹介
ヴェネツィアに暮らしたこともあるジャーナリストの矢島翠さんは、著書『ヴェネツィア暮らし』の中で、《どこに行こうと、あなたはことばに突き当たらざるを得ない》《このまちをめぐって書かれてきたおびただしい書物の群れ》と語っています。(矢島翠さんの本については「ヴェネツィアブックリスト日本人作家篇」でも紹介しています)。本当に、それだけで何冊も本が書けるくらい、ヴェネツィアについては、古今東西多くの文筆家たちが言及してきました。
文化史専門家の鳥越輝昭さんは、文学とヴェネツィアとの関わりを纏めた『ヴェネツィア詩文繚乱』という本の中で、《この世の最大の喜びはヴェネツィアを訪れることである。それに次ぐ喜びは、ヴェネツィアに書いたものを読むことである》と、まえがきを結んでいます。今回は、そんなヴェネツィアについて語られた数多の古典や名作の中から、日本語訳が手に入りやすいものを厳選してご紹介します。刊行された年代順に並べてみましたので、ヴェネツィアに興味がある方は参考にしてみてくださいね。
⒈ シェイクスピア 『オセロー』
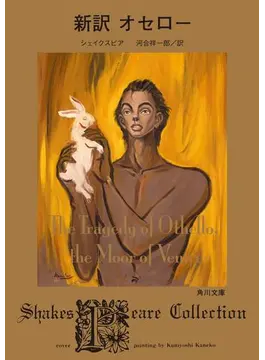
ウィリアム・シェイクスピアの四大悲劇の一つ。シェイクスピアでヴェネツィアと言えば、『ヴェニスの商人』が有名ですが、こちらの劇も副題は「ヴェニスのムーア人」となっており、ムーア人でありながらヴェネツィアの軍人であるオセローを主人公としています。ムーア人とは北アフリカのムスリムを指し、この有名な悲劇の主人公が有色人種であることは、古くから特異な事象として論議されてきました。実際のヴェネツィアは貴族制であり、移民であるムスリムのオセローが共和国軍の総指揮を務める、ということはありえなかったようですが、遠く離れた英国から見たヴェネツィアは、それだけ国際色豊かな都市だったのでしょう。『ヴェニスの商人』と並んで、他国の「ヴェネツィア」イメージの源泉となった作品です。
2ゲーテ 『イタリア紀行』
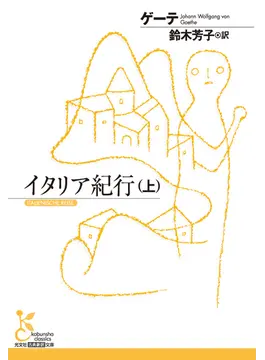
名高いドイツの詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが1786から88年にかけてのイタリア旅行について綴った有名な作品。実際には約30年後の1816年に発行されました。ローマについてのパートが大半を占めますが、ヴェネツィアについても滞在期間は1ヶ月半と僅かながらも、一章を割いて、ゴンドラの街散策から観劇、教会建築や宮殿、海軍工廠に至るまで、文豪の流麗な文章で語っています。初めてラグーナからヴェネツィアを訪れた冒頭部分、月光の中で船乗りの有名な歌を聴くシーンなどは特に有名。古典の中でもヴェネツィアの有名な風物詩がバランス良く織り込まれ、とても読みやすい作品です。
ぼくを囲むものは何もかも尊いものばかりだ。それは集合された人力の偉大なる尊敬すべき制作物であり、一君主ではなく、一民族の、見事な記念碑である。そしてたとえ彼らの潟がしだいに埋められ、邪悪な厲気が沼沢の上にただよい、彼らの商業は衰微し、彼らの権勢は地におちることがあっても、この共和国の全体の基盤とその本質とは、一瞬たりとも、これを観る者の畏敬の念をそこなうことはないだろう。
⒊アンデルセン 『即興詩人』 森鴎外訳

日本でもお馴染みの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンが、イタリア各地を舞台に初めて書いた長編小説。1835年に刊行され、日本では森鴎外が約10年の月日をかけて日本語訳を完成させ、その典雅な文章と共に日本の知識人たちに流布しました。作家の須賀敦子さんも、イタリアに留学して最初に父親から送られてきたのがこの本だったと書いていますし、画家の安野光雄さんもこの本を片手にイタリアを旅したとか。日本人にとってのいわばイタリア旅行のバイブル的存在だったようです。<いのち短し 恋せよ乙女>の吉井勇の作詞で一世を風靡した「ゴンドラの唄」も、この本に出てくるヴェネツィア民謡が元になっているとのこと。山川出版社による口語訳の本もありますので、現代ではちょっと難しい森鷗外訳の参考にしながら読むこともできます。
⒋ ジョン・ラスキン 『ヴェネツィアの石』
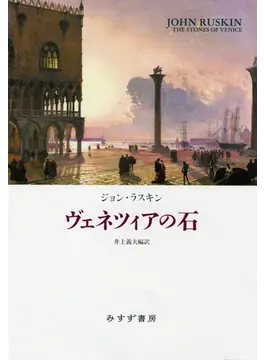

イギリス・ヴィクトリア時代を代表する美術評論家のジョン・ラスキンが1853年に刊行したヴェネツィアの建築史。ラスキンのルネサンスやバロック美術を批判し、それより前のゴシック美術に重きをおく価値観は、19世紀末のゴシック・リヴァイバルやアーツ&クラフツ運動などに大きな影響を与えました。全3巻になる膨大な原書から主要部分を抜粋した本書は、ラスキン生誕200年を記念して2019年にみすず書房から出版されたもの。抜粋と言っても、建築史の専門的な記載も多く、決して読みやすい本ではありません。また、ラスキンの史観や美術論は、ある意味でかなり偏ったものですので、一般的な美術史やヴェネツィア史を知る上で最適、というわけではありませんが、西欧知識人たちの「ヴェネツィア」イメージに大きな影響を与えたという意味で、一度読んでおいて損はない本です。ラスキンの格調高い文章も秀逸。
それゆえに、いやしくもこのような真実に思いいたす価値があるなら、読者よ、私のもとに来たれ。そうして私とともに知ろうではないか。この「海の都市」の街路に分け入る前に、はたして文目も分かぬその魅惑に身を委ねてよいものかどうかを。夏の暮れ方、都の高楼に刻まれた最期の変化に、雲の峰の生む奇想のごとく眺め入り、そのまま夜の闇に沈むに任せるべきなのかどうかを。あるいはむしろ、うずたかく明るい高楼の大理石は、波がやがて成就させたときに掻き消える「海の都市」の奢侈に対する宣告ー「神は汝が王国の命数を定め、これを終わらせ給いぬ」という言葉ーを記したページとして見るべきではないかどうかを。
⒌アンリ・ド・レニエ『ヴェネツィア風物誌』
アンリ・ド・レニエは、現代の日本ではあまり知られていませんが、永井荷風が「黄昏の詩人」として寵愛し、20世紀にフランスで活躍した詩人・小説家です。レニエはヴェネツィアに関する作品を50篇ほど残していると言われ、のちのフランス人の「ヴェネツィア」イメージ形成に決定的な役割を担っています。『ヴェネツィア風物詩』は、マルセル・プルーストに「すばらしいエチュード」と絶賛された画家マルセル・ドトマの挿絵とともに、レニエの2篇の韻文詩と15篇の散文詩を掲載、1906年に刊行されました。フランス文学者の窪田般彌さんが、1992年に王国社より口語訳の本書を刊行。平凡社ライブラリーでは文語体の翻訳である『水都幻談』として出版されています。
全く、ここは奇異なる美しさの漂う不思議な土地ではないか?その名を耳にしただけで、心には逸楽と憂愁の思いが湧き起こる。口にしたまえ、《ヴェネツィア》と、そうすれば、月夜の静寂さのなかで砕け散るガラスのような物音を聞く思いがしよう、、、《ヴェネツィア》と。それはまた、陽の光を受けて引き裂ける絹の織物の響きさながら…《ヴェネツィア》と。そして、色という色は入り混じって、変わりやすい透明な一色となる。この地こそは、まさに妖術と魔術と幻覚の土地ではないか?
⒍トーマス・マン『ヴェニスに死す』
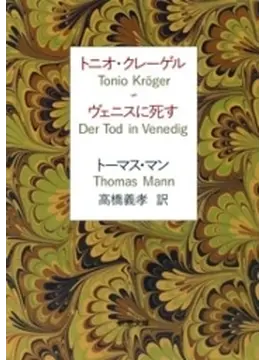

言うまでもなく、ノーベル文学賞受賞した偉大なるドイツ人作家トーマス・マンの代表作です。1911年に実際に作者がヴェネツィアを旅行し、そこで出会ったポーランド人の美少年にインスパイアされて書いた作品と言われています。タイトルにヴェニスを冠した文学作品としては、シェイクスピアの『ヴェニスに死す』と並んで、世界で最も有名な作品でしょう。日本では、ルキノ・ヴィスコンティ監督による映像美溢れた映画作品の方が有名ですが、こちらの原作は風景描写よりは、哲学的な引用や省察の多い作品になっています。それでも、主人公が船でヴェネツィア入りするシーンや、疫病の潜んだ街並みを徘徊するシーンなど、ヴェネツィアの風情が味わえる描写も多く、映画とはまた違った典雅な文章による文学的描写を楽しめます。
かくしてかれはふたたび、あの最もおどろくべき埠頭を見た。この共和国が、近づく航海者たちのうやうやしいまなざしにむかってかかげてみせる、幻想的な建築物のあのまばゆい構図を見たのである。ー宮殿の軽快な華麗さとためいき橋と、水ぎわの獅子と聖者のついた円柱と、童話めいた殿堂のきらびやかに突き出ている側面と、門道と大時計を見とおすながめとーそしてかれは、じっと見やりながら、陸路をとってヴェニスの停車場に着くというのは、一つの宮殿の裏口からはいるのにひとしい、そして人はまさに、今の自分のごとく、船で、大海を越えて、都市のなかでの最も現実ばなれのしたこの都市に到達すべきだ、と考えた。
書評記事はこちら
⒎マルセル・プルースト『失われた時を求めて第6篇消え去ったアルベルチーヌ』
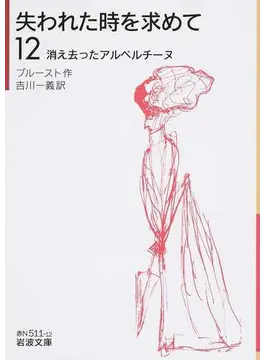

20世紀最大最長の小説『失われた時を求めて』の作者、プルーストもまた、ヴェネツィアと深い関わりを持つ作家です。1925年に上梓された第六篇『消え去ったアルベルチーヌ』の後半では、傷心の主人公がヴェネツィアを旅して回ります。「記憶」が最大のテーマの一つであるこの作品の中で、このヴェネツィアの「記憶」は大きな役割を担います。主人公の故郷コンブレーの記憶とヴェネツィアの記憶が重ねて語られているのも印象的で、プルーストにとってヴェネツィアが特別な意味を持つ場所であったことが分かります。プルーストはラスキンの『ヴェネツィアの石』を愛読しており、1900年にヴェネツィアを訪れた際にもこれを携行していたそうです。また、先に紹介したレニエの『ヴェネツィア風物誌』の挿絵を描いたドトマの絵画についてもここで書かれています。ラスキンを敬愛していたプルーストらしく、ヴェネツィアの建築物についての描写は一際美しく、その他にも、サン・マルコ寺院のモザイク、カルパッチョの絵画、ガラスやレース工場、市場で働くヴェネツィア女たち、ゴンドラでの散策、運河沿いの高級ホテルなど、ヴェネツィアの色々な風物が、この小説独特の流麗な文章で綴られています。
夕方になると、私は魔法にかけられたようなこの町のなかに、ひとりで出かけてゆく。知らない区域に入りこむと、自分がまるで『千一夜物語』の登場人物になったような気がする。行き当たりばったりに歩いてゆくうちに、どんなガイドブックも旅行者もふれていなかった未知の広々とした広場を見つけないようなことは、ごく稀だった。
⒏ヨシフ・ブロツキー 『ヴェネツィア・水の迷宮の夢』
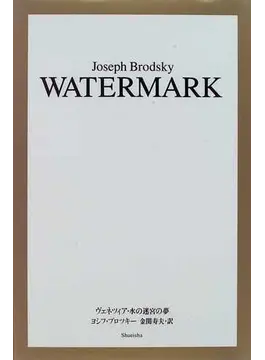

ノーベル文学賞を受賞したロシアの作家・詩人であるヨシフ・ブロツキーが冬のヴェネツィアをモチーフに綴った、散文詩のような美しい自伝的短編小説。原題は英語で「Watermark」といい、須賀敦子さんも著書の中で、この本について触れています。若い頃にレニエの小説を読んでからヴェネツィアに憧れていたブロツキーは、アメリカに亡命して以来、大学の冬休みを利用して17年間毎年のように冬のヴェネツィアに通ったと言います。「水」と「時」を重ね合わせ、冬の静かなヴェネツィアの町に「自分」を見る、時にユーモラスで時に深遠な文章はとても印象的で、20世紀の新しいヴェネツィアの「古典」と言えます。
ぼくは自分自身に誓った、もしもいつかぼくの住む帝国の支配から逃れることができたなら、もしもいつかバルト海からこのウナギがなんとか抜け出すことができたなら、なにはさておき、まずヴェネツィアへ赴き、ボートが通る度に波しぶきが窓にかかるような館の一階に部屋を借りて、しめった石の床でたばこを揉み消し揉み消し、書くのは哀歌(エレジー)二、三篇。咳をし、酒を飲む。そしていよいよ軍資金が残り少なになってきたら、汽車には乗らず、代わりに小さなブラウニング式ピストル一挺を買いこんで、自分の脳天を撃ち抜く。ヴェネツィアでは、自然死というのは、やはり出来ないのだ。
繰り返してみよう。水は時であり、自らの分身を通して美を与えてくれる。僕らもその一部は水であり、ぼくらもまたそのようにして美に仕える。この町は水をこすって、時の容貌まで改良する。未来を美化する。それこそが宇宙の中の、この町の役割である。ぼくらは動くのに町は動かないからだ。涙がその証拠だ。ぼくらは去り、美はとどまるからだ。ぼくらは未来に向かっているが、美は永遠の現在だからだ。涙は美のもとに残ろうとする。そこにとどまろうとする。この町の中に融けこもうとする。しかしそれはルール違反だ。涙というのは一種の投げ返し、未来から過去への贈り物だ。あるいはそれは、より小さなものからより大きなものを差し引いた結果なのかもしれない。たとえば人から美を。そして愛についても、同じことが言える。なぜなら人の愛もまた、その人そのものよりはもっと偉大だからだ。
<番外編>
今回ご紹介した他にも、ヴェネツィアに触れた有名な古典作品は数多くあります。シャトーブリアンにジョルジュ・サンド、ミュッセ、テオフィル・ゴーティエ、シェリー、オスカー・ワイルド、チャールズ・ディケンズ、バルザックに、ヘンリー・ジェイムズ、ツルゲーネフ、ヘミングウェイ。
特に、英国の詩人バイロンは、『チャイルド・ハロルドの巡礼』の他、ヴェネツィア元首を主人公にした詩劇『マリノ・ファリエロ』などが有名で、西欧人一般の「ヴェネツィア」イメージに大きく寄与しましたが、残念ながら、現在邦訳の本が手に入らないので、今回のリストからは外しました。『チャイルド・ハロルドの巡礼』は、註解付きの訳本第三巻までが九州大学出版会より刊行されていますが、残念ながらヴェネツィア記を含む第四巻は刊行されていません(2021年現在)。
<参考>
⒈ 『ヴェネツィア詩文繚乱 文学者を魅了した都市』 鳥越 輝昭
⒊ ブログ『イタリア、とりわけヴェネツィア』(ペッシェクールドさんのブログ)






コメント